 インドの貧しい人々とともに働き、「神の愛の宣教者会」を設立し、その活動は全世界に及びました。1997年に没した後、03年に福者、16年には聖人に列せられました。
インドの貧しい人々とともに働き、「神の愛の宣教者会」を設立し、その活動は全世界に及びました。1997年に没した後、03年に福者、16年には聖人に列せられました。マザー・テレサ 列聖決定
バチカン放送ほかによると、3月15日、バチカンで開かれた枢機卿会議において教皇フランシスコは、マザー・テレサほか4人の列聖を承認する教令に署名しました。
マザー・テレサは1910年、現在のマケドニア・スコピエ生まれ。学校教育を行う女子修道会に入会。インド・コルカタで教員をする中、同地のより貧しい人々と働く呼びかけを受け、こうした活動に専心するようになりました。さらに「神の愛の宣教者会」を創設し、長年、最も過酷で貧しい人々のために世界中で働き、その後継者たちを育ててきました。
1997年に亡くなったのち、2003年10月19日に、教皇ヨハネ・パウロ2世によって列福されました。昨年12月には、脳しゅようを患っていたブラジル人男性の回復が、教皇フランシスコによって2つ目の奇跡として認められ、列聖の決定が待たれていました。
列聖式は、ことし9月4日に行われる予定となっています。
(2016.3.17)
マザー・テレサ 逝去
1997年9月5日(日本時間9月6日の午後6時)にマザー・テレサは、87才の生涯を閉じまし た。
マザーテレサ逝去に際して発表されたコメントを中心に掲載しています。
マザー・テレサ DVD
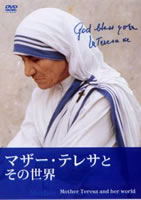
マザーテレサとその世界
監督:千葉茂樹
本編:55分(日本語、英語)
発売元:女子パウロ会
- 女子パウロ会のホームページよりお求めになれます。
略歴
- 1910年8月27日
- 旧ユーゴスラビアのスコピエ(現マケドニア旧ユーゴスラビア共和国)に生まれる。アグネス・ゴンジャと命名される。(花のつぼみの意)。父:ニコラ・ボアジュ、母:ドラナフィル、長女:アガ、長男:ラザール 父は商人。
- 1919年
- アグネス9歳の時、父死亡。
- 1925年
- イエズス会のヤンブレンコヴィッチ神父が作った聖母マリアの信心会が、アグネスの生涯に多大な影響を与えることになる。信心会の会員たちは様々な聖人の生涯や宣教師たちの活躍を調べていたが、とくにユーゴスラビアからインドのベンガル地方に派遣されていたイエズス会司祭たちの生き方に心を動かされ、ベンガル宣教地での献身を決心する。
ベンガルではアイルランドのロレット修道会が活動していたので、この会に入会しようと決める。
- 1928年9月15日
- アグネスアイルランドのロレット修道会に入るためにスコピエを去る(18歳)。
- 1928年12月1日
- ダージリンで修練を始めるために、インドに派遣される。
- 1929年5月23日
- 修道名としてテレサと改名。修練者としてダージリンで修練を始める(19歳)。
- 1931年5月24日
- 清貧・貞潔・従順の初誓願をたてる。(21歳)
- 1929年-48年
- コルカタ(カルカッタ)の聖マリア高等学校で地理を教え何年間かは校長を勤める。
インドで創立された修道会である「聖アンナの娘修道会」の指導をする。
- 1937年5月24日
- 終生誓願をたてる。聖マリア高等学校校長となる。
同時に修道院外にある聖テレサ女学校でも教えることになり、スラムの貧しい人々をまのあたりにする。
- 1946年8月16日
- 暴動のため、コルカタの町は大混乱に陥る。テレサ、町に食糧を探しにでかける。
- 1946年9月10日
- 「決意の日」。黙想会に出席のため、ダージリンに向かう汽車の中で、「貧しい人々とともにいるキリストに尽くしなさい」という神のうながしを感じ、コルカタのスラムで働く決意をする。修道会を退会し、スラムで働く許可を目上に願い、その願いは、教皇庁に送られる。
- 1948年7月末
- 4月12日付の退会許可書が出る。(38歳)
- 1948年8月8日
- ロレット修道会の修道服をぬぎ、水色にふちどり、肩に十字架をつけた白いサリーを身にまとった。3か月間、パトナのアメリカン医療宣教修道女会経営の「聖家族病院」で、看護の集中訓練を受ける。
- 1948年12月21日
- 最初のスラム街学校開設の許可を得、子どもたちを集めて青空教室を始める。
- 1949年2月
- アパート生活を始める。(39歳)
- 1949年3月19日
- 最初の協力者であるベンガル人の若い娘がテレサの活動に参加。
この若い女性は、テレサの聖マリア高等学校での教え子で、後に、マザー・テレサの補佐役をつとめるシスター・アグネスである。
- 1950年
- テレサ、国籍をユーゴスラビアからインドに移す。
- 1950年10月7日
- ミッショナリーズ・オブ・チャリティー「神の愛の宣教者会」を創立し、コルカタ大司教より認可を受ける。この時、メンバーは12人になっていた。この時から、シスター・テレサは、マザー・テレサと呼ばれるようになった。その後、会員が増え活動も増えた。インドを中心に世界55か国に211の修道院が開設され、会員は2000人を越えした。
- 1952年
- 「死を待つ人の家」開設。(42歳)
「死を待つ人の家」の本当の名称はヒンズー語で「ニルマル・ヒルダイ」(清い心の家)である。ヨーロッパのジャーナリストが「死を待つ人の家」と呼び始めて一般化したもの。
- 1953年
- マザー・テレサと28人のシスター、修道会本部となる家をイスラム教徒から提供され、引っ越す。
- 1953年4月12日
- 神の愛の宣教者会で終生誓願。
- 1955年
- 初めての「孤児の家」が開設される。(45歳) 「孤児の家」はヒンズー語で「シシュ・バハン」と呼ばれている。
- 1959年
- ハンセン病診療所開設。(49歳) ハンセン病診療所は「平和の村」と呼ばれている。
- 1960年
- アメリカ、イギリス、イタリアを訪問。ローマで30年ぶりに兄のラザールと再会。(50歳)
- 1963年3月25日
- マザー・テレサの活動に賛同する男性が、マザー・テレサの指導の下に「神の愛の宣教者会」(ブラザーの会)を設立。同会、コルカタ大司教によって認可される。
- 1964年
- ローマ教皇パウロ六世インド訪問の折、謁見。教皇帰国に際してインド滞在中乗っていた車をプレゼントされ、マザー・テレサに残す。彼女は、それを売り、貧しい人への奉仕にあてる。
- 1965年2月1日
- 「神の愛の宣教者会」教皇認可を受ける。ベネズエラにセンター開設。
- 1967年
- セイロンのコロンボに修道院開設。
- 1968年
- タンザニアのタボラに修道院開設。ローマのスラム街に修道院開設。
- 1969年
- オーストラリアのバークに原住民のためのセンター開設。
- 1969年3月26日
- マザー・テレサ共労者会が設立され、教皇パウロ六世の認可を得る。(現在、全世界に会員7万人)
- 1970年4月
- メルボルンへ。7月 アンマンへ。
- 1970年12月8日
- ヨーロッパとアメリカ各地の志願者を養成するため、ロンドンに修練院を開設。
- 1971年1月6日
- パウロ六世教皇より、ヨハネ二十三世教皇平和賞受賞。
- 1972年
- ジョン・F・ケネディ賞受賞。
- 1975年
- 「神の愛の宣教者会」創立25周年を迎える。施設の数はインド国内に61、海外に27、シスター数は千人を越える。(1,035人)。アルベルト・シュバイツアー賞受賞。
- 1976年11月
- アジア宗教者平和会議に出席(シンガポール)。
- 1978年4月
- 東京に修道士のセンター開設。
- 1979年12月10日
- ノーベル平和賞受賞。ノルウェーのオスロで記念講演。
「私はノーベル平和賞にふさわしい者ではありません。けれど世界中の貧しい人々に代わって、この名誉ある賞をいただきます。私のための受賞晩餐会はいりません。どうぞ、そのお金を貧しい人々のためにお使い下さい。」記念スピーチ賞金の19万ドルは、飢えに苦しむ人々の食料、人々から見放された孤独な人々のホームの建設資金に当てられた。
- 1981年4月22日
- 初めて日本を訪れる。修道誓願金祝を祝う。
- 1981年5月24日
- 東京に修道院を開設。
- 1982年4月21日
- 2度目の来日。
- 1983年11月
- エリザベス女王より、優秀修道会賞を受賞。
- 1984年
- 「神の愛の宣教者会」(司祭の会)創立
- 1984年11月
- 3度目の来日。
- 1985年
- エチオピアへ。
- 1986年
- パリで行われた第9回国際ファミリー会議に出席。
- 1989年
- 「神の愛の宣教者会」の修道院はインド国内に159、海外に230。
- 1990年9月
- 心臓病で入院。一時は再起を危ぶまれるが、回復し10月退院。ペースメーカーを埋め込む手術を受ける。
- 1991年3月2日
- ティラナでの活動を開始するため、アルバニア訪問。
- 1991年5月
- バングラディッシュのサイクロン被災者の緊急援助に当たる。
- 1991年12月26日
- メキシコのティファナ訪問中、肺炎にかかり、一時危篤に陥る。
アメリカ、カルフォルニア州ラホヤのスクリップス病院に入院。手術を受ける。
- 1992年1月15日
- カルフォルニア州ラホヤのスクリップス病院を退院。
- 1992年2月
- アルバニア政府、マザー・テレサにアルバニア市民権を授与。
- 1992年8月4日
- ニューヨークで、コロンブス騎士会のガウデイム・エト・スペス賞受賞。
- 1997年9月5日
- 永眠
- 1997年9月13日
- コルカタで国葬が行われる。
マザーハウスに埋葬されている。
- 2003年10月19日
- 教皇ヨハネ・パウロ二世により、福者に列される。
- 2016年9月4日
- 教皇フランシスコにより、聖人に列される。
